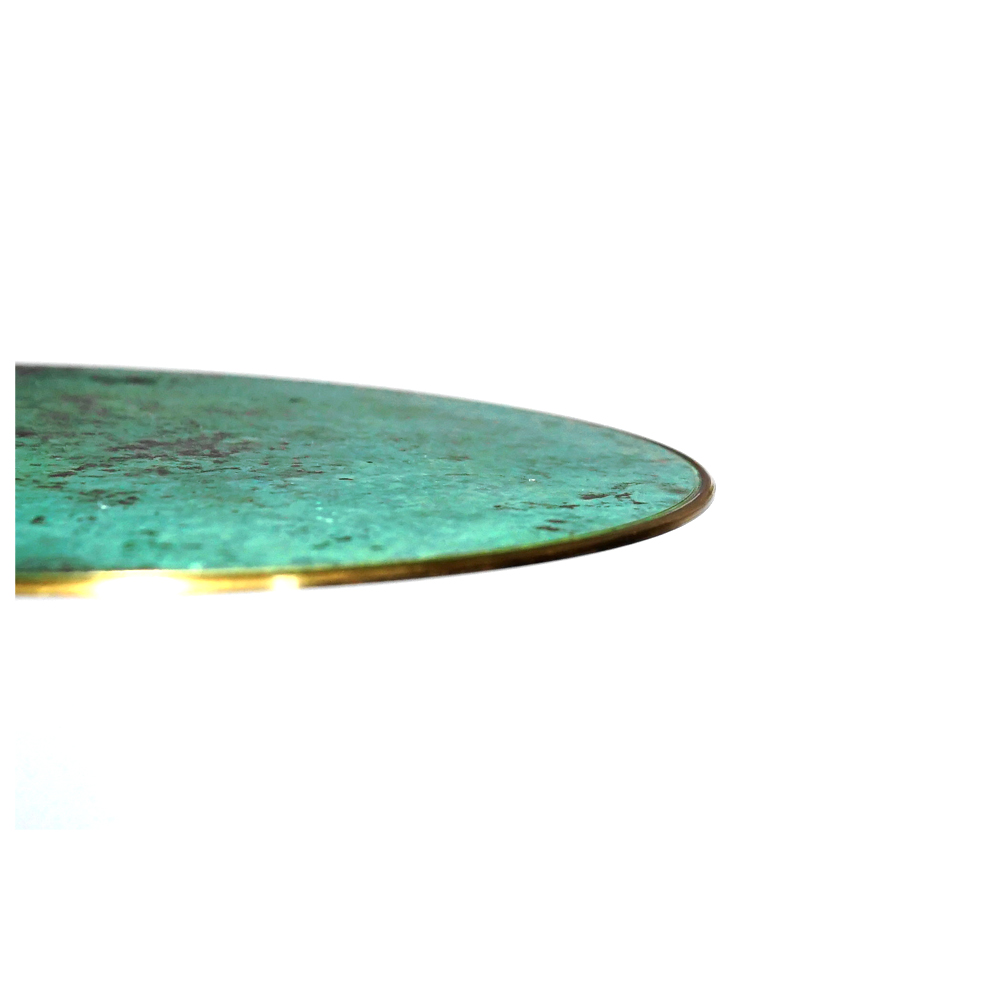御印祭(ごいんさい)は、藩主利長公より拝領した宅地を始め、
多くの手厚い保護に対して報恩感謝の誠を捧げ、藩主のご命日に遺徳を偲ぶためのものです。
慶長十九年五月二十日がご命日ですが、明治六年に、旧暦の五月二十日が、新暦では六月二十日になったのです。このお祭りは、利長卿死後間もなく起こったものと想像されます。

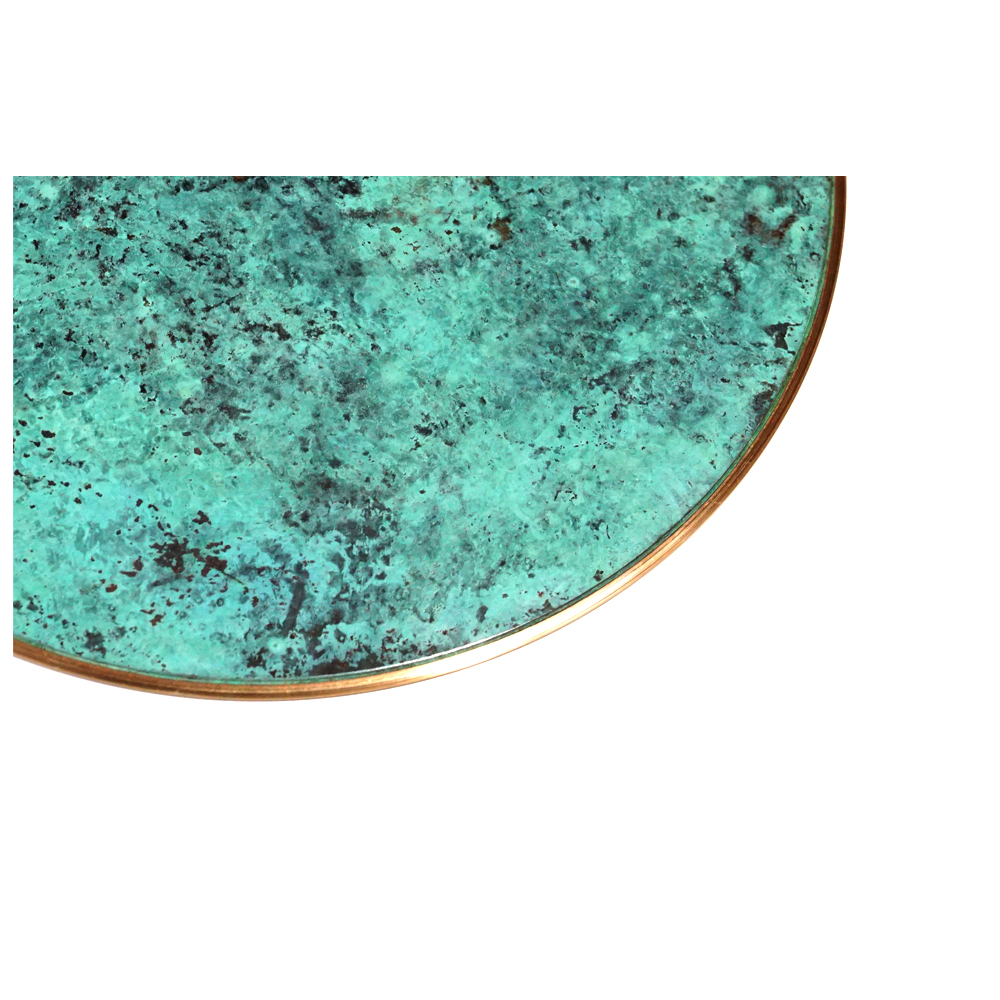
弥栄節(やがえぶし、通称やがえふ)は、約400年の伝統を持つ高岡鋳物作りの作業歌である。かつて、職人たちが、鉄を溶かすために溶解炉に強い風を送るとき、「たたら」という足で踏む大きな「ふいご」を使用した。この「たたら」踏みは重労働であり、弥栄節は、職人たちが重労働の苦痛をまぎらわし、多人数で行う「たたら」踏みの拍子をそろえるために唄われた。弥栄節は、「エンヤシャ、ヤッシャイ」「ヤガエー」の掛け声に合わせて、法被姿に鉢巻き、手に竹の棒を持った男性が地面を強く踏む鋳物師をイメージした踊りが入る。高岡鋳物発祥の地である高岡市金屋町で毎年6月19日に行われる御印祭(ごいんさい)(町の基礎を築いた加賀藩2代藩主前田利長を偲ぶ祭り)の前夜祭で、弥栄節の町流しが行われ、踊り手が町中を踊り歩き、弥栄節が響き渡ります。